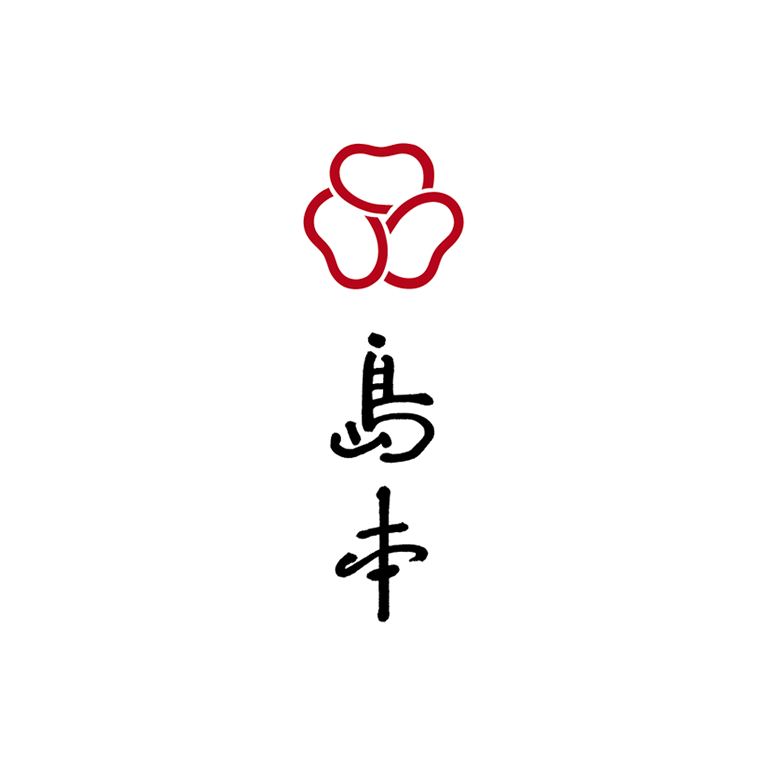三隈川かっぱめし
ヤブクグリの弁当第2弾として「三隈川かっぱめし」を企画。かつて、山で伐った材木を、筏に組んで、川を使って運んでいたように、「山」と「川」は、密接に繋がり、林業を支えていました。山のイメージ「日田きこりめし」と川のイメージ「三隈川かっぱめし」で、山と川が一緒になって大分県日田市の知名度を広げていければと考えたのがこの企画の原点です。 ヤブクグリのメンバーの半数以上が、日田市内在住ですが、昔のようにみんなが三隈川で泳いでいるような川にしたいと考え、清流の象徴として「かっぱ」をモチーフにしました。また、三隈川の清流を下流域の人たちへも届け共有したいという思いから、有明海の海苔で作った細い海苔巻を並べ丸太の筏のようにデザインしました。杉の木でできた弁当箱のふたをめくると長いままのかっぱ巻が三本、そして高菜、かんぴょう、キュウリの3種類とおかずは、空揚げ、漬物、卵焼きが入ってます。 包装紙には、小坂さんの日田のかっぱ伝説の小話に牧野氏の絵。箸袋には江副氏によるかっぱ占いが16種類。デザインは富田氏が担当。占いは、当たりがでたら寳屋の大将から何かプレゼントがもらえます。